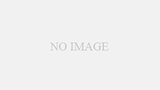※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。

こんにちは。現在建設業界でサラリーマンとしてお仕事をされていらっしゃる方は、近い将来建設業界で独立や法人設立等をお考えではございませんか?このブログで建設業許可を取得するためにどのようなことが重要になるかを簡単にまとめてみましたので、ぜひこちらを見てイメージしていただければと思います。
1.工事金額500万円をまずは基準に
まずは工事の金額についてですが、500万円以下の請負工事契約だけを行ってお仕事をしていく場合には許可は不要です。※500万円未満の工事は「軽微な建設工事」とされています。請け負う工事金額を低いもので最初に行っていく場合は必要ございません。デメリットはもし大きな仕事が入ったきた時には、営業許可はすぐに取得することはできません。
2.法人か個人か
個人(個人事業主)でも許可を取得することができます。法人も可能です。法人は登記をすることにより設立しますが細かいことは割愛します。個人事業主(建設業許可取得とは別)を行うことにあたっては特に手続きなど不要で始めることができます。※建設業許可ではなく個人事業主の手続きです。※開業届けなどはお出しください。
3.建設業の許可区分
建設業の営業所を一つしか設けないのであれば、知事許可、複数の都道府県に営業所が存在するのであれば大臣許可というものになります。細かなことはさておき、まずは「営業所が複数あり都道府県ごとに営業所が存在するか」をイメージください。
※例えば東京都内に一つだけ、ですとか東京都と埼玉に一つずつ営業所ある、等の違いです。
4.一般か特定か
工事金額4000万円(建築工事業6000万円)を基準にお考え下さい。
一般建設業許可と特定建設業許可があります。
【一般建設業許可】は
・下請けに出さないで工事をする
・もしくは下請けに出しても下請契約が4000万円未満(建築一式工事なら6000円未満)
※現在の建設業許可を有しているほとんどの方がこちらに該当すると把握しております。
【特定建設業許可】は
・直接工事を請け負った工事が4000万円以上(建築一式工事なら6000円以上)で下請け契約に工事をお願いする場合
※とても大きな建設会社をイメージください。
※下請け会社から⇒孫請け会社に下請けする場合は上記【特定】に関する条件はあてはまりません。あくまで直接まず元請が受けてそこから下請け契約の金額をどうするかの話になります。
5.知事許可と大臣許可の違いはなにか?
◆知 事 許 可 ……… 一つの都道府県のみに営業所がある場合
◆国土交通大臣許可 ……… 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば、東 京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その 本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の道府県でも行うことができます。 大臣許可に該当するかどうか不明な場合は、国土交通省関東地方整備局に御相談ください。 ※「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所で、最低限の要件 としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、 電話、机等、什器備品を備えていることが必要です(P6参照)。
6.許可を取ったら5年ごとに更新が必要
許可を取ったら5年ごとに更新の手続きが必要で、有効期限の30前までに行う必要があります。※手数料がかかります。
7.建設工事の分類
建設工事の内容によって29種類に分かれています。
・今行っている専門の工事を基本的に取り扱っていくことになります。
※例えば「大工工事業」、「左官工事業」、「水道施設工事業」などを細かく分かれていて許可取得の際も重要になってきます。
※建設一式工事、土木一式工事という、元請企業が統括することで行われる工事もあります。
8.重要!建設業許可を取得する為の5大要件
簡単にまとめると
要件①経営業務管理責任者がいること
※以下3つのいずかが必要
・許可を受ける工事種類について、5年以上の法人役員などの経験又は個人事業主等としての経験があること。
※例えば「個人事業主として5年以上大工工事を行っていた経験がある」等
・許可を受ける工事の種類以外の建設業に関して、5年以上の法人役員などの経験又は個人事業主等としての経験があること。
※例えば「個人事業主として6年以上大工工事を行っていた経験があり、種類は左官工事で取りたい」等
・許可を受けようとする工事の種類について、6年以上経営業務を補佐した経験があること
※例えば、「個人事業主の夫が7年間大工工事を行っており、その間配偶者や息子が補佐(経営を手伝っていた)する立場にあった場合等(6年間は手伝っていた)も含まれます。」
※経営業務管理責任者については2017年に要件が緩和されています。他業種経験が7年から6年に短縮され、他業種での執行役員経験も認められるようになりました。さらに現在、国交省はこの要件について、廃止を含め見直しの検討に入っているようです。
要件②専任技術者が営業所ごとにいること
ひとまず営業所が一つだった場合、専任技術者になる予定の方が許可を取得する工事業の国家資格などを持っている必要がります。
一般建設業なら
・大学、専門学校の指定学科卒業後3年以上実務経験を有する。高校卒業の場合は5年以上の実務経験を有するもの(学歴の有無を問わない場合は10年以上の実務経験)でかつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
※その他必要な学歴、資格に関しては細かくは国土交通省のHPで確認することができます。とても細かく規定されていますので一度HPをご覧ください。
※特定建設業は割愛します。(一般建設業許可よりも厳格になっています。)
要件③誠実性があること
・法律違反や不誠実な行為があれば建設業許可を取得することはできません。
※暴力団の構成員などは許可を受けることができません。
要件④財政的基礎、または金銭的信用を有していること(次のいずれかに該当する必要あり)
・自己資本が500万円以上(資産や借金などをすべて計算して500万円以上が必要)
※例えば(貯金が450万円、車が100万円の価値で借金が50万円で計500万円)
・500万円以上の資金を調達できる能力があること
※貯金が500万円以上だと確実です。
※一定時点において500万円以上のお金が手元にあったことが重要ですので、例えば損益計算書上赤字決算となっていても問題ありません。例えば、月末に売掛金が一時的に入金されたタイミングで銀行残高証明書を取得し、その数字をもって許可申請を受けることも可能です。
※許可更新時は5年間の営業した実績を示せれば問題ございません。
※特定建設業の要件は割愛します。
要件⑤結核要件に該当しないこと
・禁固以上の刑等で処せられた場合で、刑の執行を終わった日から、5年間を経過しないもの
・不正の手段により許可を受けたもの、うその申請をしたもの
・成年被後見人ではないもの
等
以上が建設業許可を取得する上で必ず知っておいたほうがいい情報をまとめました。
今後許可取得をお考えの方はぜひご確認ください。次回は建設業許可を取得する上での費用などをお伝えする予定です。
当事務所でも建設業許可に関するご相談や依頼を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
—
東別府拓真行政書士法務事務所
#東京都北区行政書士
https://higashibeppu.com/
03-6821-0221