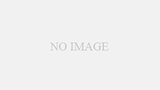※当記事は,当事務所の旧サイトから本サイトへの移行の為転載したものです。
契約書の作成をすること、チェックを行うことは様々な会社で行われていること思います。行政書士も契約書の作成やチェックを行うことがあります。
契約書は何のために作成し、作成したりチェックを行う上で何を注意しなければいけないか、契約書を作成する目的についてご紹介していきたいと思います。

契約書とは、というよりそもそも契約をすることとは
契約自由の原則というものがあります。契約とは、当事者の意思の合致により成立するものです。もう少し難しくいうと法律効果をもたせるものです。
契約については、契約自由の原則がとられ、
①契約を結ぶか否か、及び誰を相手方とするか(契約成立の自由)
②どのような内容の契約を結ぶか(契約内容の自由)
③どのような形式で結ぶか(契約方式の自由)
以上について自由に合意をすることができます。しかし、限界もあります。
契約自由の原則は、対等な個人がその合理的意思に基づいて合意をすることを念頭に発展してきたものですが、現代の社会においては、契約当事者間の台頭が望めない局面で契約が締結され、契約の内容も一法の利益に偏したものになりがちです。そこで各種立法や判例理論により国家が積極的に干渉し、弱い立場契約当事者を保護しようとする試みがなされているわけです。つまり法律(強行法規など)に反する契約はできないということになります。
契約書作成の意義
しかし、法律などでの限界はあっても、契約自由の原則は妥当する範囲はとても広範にわたりますので、いったん当事者が合意して契約が成立してしまえば、その契約は当事者を強力に拘束してしまうでしょう。
以上の理由により、当事者、多様な方法で利益を得られる可能性を享受しますが、それとは反対に、予測不可能なリスクにさらされる可能性もあるともいえます。契約をする当事者としてはいかに契約から生じた利益(債権)を確保するか、そしていかに紛争を防止するかという問題意識につながっていきます。
以上により契約書は、上記問題に対応するために必要不可欠なものであるとご認識いただけるかと思います。
紛争を予防する為に(リスク回避)
もしあなたが口約束だけで相手方と約束(契約)をしてしまい契約書を作成しなかったら、後々問題が発生することが容易に想像できるのではないでしょうか?
突然相手方がそもそも約束をしていないといいだすかもしれない。
突然相手方が金額が違うと言い出してくるかもしれない。
など想像ができますね。
このように口頭だけの契約では、契約の有無及び内容自体について、後日紛争が生じる可能性があります。また、口頭だけで進めた場合、あまり細かい内容までは取り決めないのではないのではないでしょうか?あいまいなやりとりで終わってしまったため、言葉の認識や解釈が違っていて後々問題になることがあります。そのささいな誤解こそがそもそもの紛争の端緒であることも多いわけです。
このようことにならないよう契約書を作成して、契約条項を誤解のない簡潔かつ明瞭な語句で書面に記載することが重要になってきます。
紛争防止の為に契約書を作成することが一つの目的です。注意しなければならないのは、契約の自由はどこまでも無制限に契約できるわけではなく、法律や判例などで制限を受けることもあります。例えば強行法規に反する契約条項は効力をもたないので、当事者が期待していた利益を得られないことはもとより、場合によっては行政処分、刑事罰の対象となる可能性も出てきます。契約再生にあたっては、関連法規・判例などを十分に精査し、危険な条項を発見した場合は、これを排除しておく必要があります。
債権の管理や回収の為に
契約をしたら何かしらの利益を得ることにあるので、その利益を管理して最終的に回収することは当事者にとって一番の目的だと思います。何かしらの利益を「債権」と言っています。逆になにかをしなければいけない義務のことを「債務」といいます。
例えば、100万円で車を売ったが、結局100万円を払ってもらえなかった。などです。
車を渡したんだから100万円を受け取る権利(債権)はあるとどなたでも明白にお分かりになると思います。
このような、相手方が車を100万円の代金を渡してくれない時に強制的に回収する為に訴訟、そして強制執行にたよることになります。
その際には車の売買に関する「契約書」があれば知れが「照明文書としての役割を担うことになります。契約書がこの役割をはたすためには、文書の中に契約条項が記載されていることと、契約当事者が明示されていて、その者の押印があることが最低限備えるべき条件となることでしょう。
契約上の自己の得られる利益(債権)を回収できるように契約書は大変重要な役割をもっています。
なお、また速やかな債権回収を図りたいのであれば、契約書を公正証書で作成するといいでしょう。
よい契約書とは
市販されている契約書のサンプル書式があります。これを参考にしたとしても必ず自己(自社)のその時の契約に当てはまらないものも出てきます。その際は必ず個別に条項を増やしましょう。また、会社では新担当者が会社の契約書を深く知らないまま、あるいは何も考えずに利用しているとトラブルが発生したときに的確な処理をすることができないと思います。
・契約書は自己の利益に合うようしっかりと精査する必要がある。
・契約の内容を把握しておきトラブルが発生した時も的確な処理ができるようにしておく。
契約書を作るには想像力が必要だといわれますが、これは自らの取引の的確な分析に立って様々な事態を事前に想像する力が必要だということです。
逆に、自らが一方的に有利な条項を記載すること、つまり一方だけが一方的に利益を得られる契約は不公正な契約内容ということで裁判所がその効力を否定する場合もあり望ましいものではありません。あっくまでも契約の内容は双方の利益と不利益が公正でバランスがとれている必要があります。
予防法務について
既に発生した紛争に対処する為に臨床法務という言葉がありますが、将来発生するかもしれない事態をあらかじめ予測し、対応しておく必要があるものに予防策を講じておくことが必要となります。このことを予防法務といいます。
戦略的法務について
こちらは紛争を防ぐ予防法務を超えて、リスクを低く抑えつつ、いかに利益を最大化するかという能動的・経済的側面が重視されてきています。各条項のリスクの検討や対処だけではなく、契約全体を見たリスク及び利益の検討、さらにほかの取引も含めた全体からみてどう評価すべきかをチェックする視点が必要になってきます。このようなことを戦略的法務と言っています。
以上、契約書を作成する目的をまとめてみました。当事務所でも契約書作成やチェックを行っています。契約書の作成やチェックには種類や量によってご依頼料金が変わってきますのでまずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/