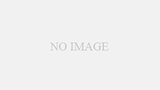寄与分についてご存じでしょうか?相続の際、被相続人の介護などを行っていた場合等、寄与分を知っておいた方がいいです。この記事では「寄与分」についてご紹介します。
寄与分(きよぶん)とは
「寄与分」とは、共同相続人中に、被相続人の持参の維持、または増加について特別の寄与をしたものがある場合に、その寄与を行った相続人に対して相続分以上の持参を取得させる制度をいいます。
(民法904条2項)
相続人が介護したとしても、子は親に対し扶養義務を持ちますので、通常の親の介護が寄与分として対価に反映することはほとんどありません。
どうやって寄与分は決定するのか?
寄与分は共同相続人全員が話し合い、額を決めることになるので簡単にはいきません。決まらないときに家庭裁判所が判断を下しますが、対価はまり期待できるものではありません。
介護をしていると、その先には必ず相続問題が待っています。平等は公平でありません。
このような場合は、親が生前に遺言により公平な相続分を決めておいた方がいいでしょう。
寄与分を請求できる対象者
現実に遺産分割に参加できる共同相続人に限られます。例えば、お父さんが亡くなった時の、お母さん(配偶者)とご子息で、ご子息がお父さんの介護をしていた、等の場合です。
しかし、今般の民法改正により、寄与分を請求できる範囲が広がりました。
具体的に寄与分を主張できるのは、相続人以外の一定の親族で、6親等内の血族と、3親等内の姻族が対象です。上記の例で言うとご子息の奥様が介護をしていてもそれは対象外になっていたが、改正により請求できるようになったわけですね。
・代襲相続人も請求可能です。
・養子も請求可能です。
寄与分を主張するためには
①寄与行為の根幹
⇒寄与行為は、主として無償かこれに準じるものである必要があります、相当の対価を得ていれば主張できない可能性があります。
例えば、無償で被相続人の介護をしていた等
②特別な寄与行為
⇒特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいいます。夫婦間の協力扶助義務だとか同居の親族の相互扶けあいの義務の範囲内での行為であれば、認められない可能性があります。
つまり最初から親族を助ける義務があり、通常考えられる以上に寄与していなければならないというわけです。
遺言で先に寄与分を決めてもらっていた方がいい
寄与分が認められるには、厳格な要件があって簡単には認められないので、可能であれば被相続人に遺言で寄与分のことを書いてもらえるのが一番話が早く、全員が納得できるのではと思います。
以上、寄与分に関する記事でした。当事務所でも遺言相続の相談やご依頼を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。
東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/