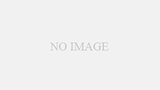昨年の7月の参院選の一票の格差が最大3倍だったことに対して選挙無効を求めた裁判の判決が18日に最高裁より言い渡される。
一票の格差とは
憲法の要請は、国民が同じ重みの一票を投じて議員を選んで、主権者として「平等」に国政に関与できること。
昨年の参院選では、最少だった福井県選挙区が約65万人だったのにたいし、最多だった宮城健選挙区は約194万人で、これはふくいの有権者と比べると宮城の人の一票の価値は0.33票分しかないので国政に意見を反映させづらくなっています。
今までにもなんども「一票の格差」の裁判があった
1964年 4.09倍 合憲
1974年 5.08倍
1983年 5.26倍 合憲
1986年 5.37倍
1987年 5.56倍
1988年 4.97倍
1996年 6.59倍 違憲状態
1998年 4.97倍 合憲
2000年 4.98倍 合憲
2004年 5.06倍 合憲
2006年 5.13倍 合憲
2009年 4.86倍 合憲
2012年 5.00倍 違憲状態
2014年 4.77倍 違憲状態
2017年 3.08倍 合憲
2020年 3.00倍 18日に判決がでる
※なにも書かれていないのは、小法廷での判決です。
参考:昭和60年の衆議院議員定数不均衡訴訟、一票の格差に関する有名な判決要旨です。
「制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定のもとにおける選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差がその後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないときはじめて右規定が憲法に違反するものというべきである」という「合理的期間論」を採用している。
今までに一票の格差について多くの裁判が行われてきたことが分かります。
最高裁は「投票価値の平等は憲法の要請と認めるが、①違憲といえるほど不平等になっていることと、②前の選挙から改善しなかったことは国会の裁量権のうち」といい、①と②が両方ともそろった時に違憲とすることにしていたとのこと。①の不平等があるけれども②の改善したかどうかについて一応前の選挙から少しでも改善がなされるよう努力していた場合は「違憲状態」という中間的な判断だけでたとえば選挙無効という形にはならない。とのことを言っていました。
今回は前回の裁判がポイント
前回の一票の格差がらみの裁判で、格差の縮小ぶりだけでなく、改正法の不足に盛り込まれた「次回選挙までに選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討し必ず結論を得る」との文言にも着目していた。
今回の裁判の対象の選挙については抜本的な見直しが行われたとは言い難い状態になっているため、前回の裁判の着目点も含めどういった状態で判決がでるか注目されています。
18日に判決とのことです。
東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/