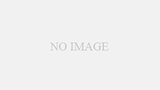相続人の範囲や法定相続分
相続が発生した際、誰が相続人になるのか、そしてどのくらいの割合で相続できるのかはご存じでしょうか。
以下、簡単にまとめましたのでお役立てくださいませ。
まずは配偶者がいるかどうかが重要
配偶者とは奥様、もしくは逆からみたらご主人になります。
配偶者は必ず相続人になります。
例えばご主人が亡くなったのなら奥様が必ず相続人なります。
次に子供がいるかどうか
次にお子様がいるかどうか確認しましょう。お子様がいて、配偶者(お母さん)もいるのであれば相続人は「配偶者とお子様」が相続人になります。
ちなみに相続分の割合は2分の1ずつになります。
ただし、お子様が複数名いる時は子供の分の「2分の1」の割合からさらに人数分で割らないといけません。そして配偶者とお子様がいらっしゃる場合は法定相続人はこれで以上で、おじいちゃんやおばあちゃんがいてもあくまで「配偶者とお子様」だけが相続人になります。
被相続人の親がいるかどうか
被相続人の親がいるかどうかです。
次は親がいるかどうかを見ていきます。ここでいう親とは、おじいちゃんおばあちゃんをイメージした方が分かりやすいです。では、配偶者がいて、子供はいない、おじいちゃんがいる場合、この場合は
「配偶者とおじいちゃん」が法定相続人になり、相続割合は
配偶者は3分の2
おじいちゃんは3分の1
になります。
お子様の時と一緒でもしおばあちゃんがいたら、上記3分の1の部分をおじいちゃんとおばあちゃんで二人で分ける形となります。
最後に被相続人の兄弟姉妹がいるかどうか
最後に亡くなった方の兄弟がいるかどうかを確認します。兄弟とは亡くなった方のご兄弟ということです。
例で、配偶者と亡くなった方の兄弟しか相続をする人がいなかった場合
配偶者は4分の3
兄弟は4分の1
の割合になります。上記のように兄弟が複数名いると兄弟の割合の「4分の1」から人数で割らないといけません。
相続人の優先順位のまとめ
①必ず配偶者が相続人になる
②お子様
③おじいちゃんおばあちゃん(尊属といいます)
④被相続人の兄弟がいるかどうか
①の配偶者がいる場合は②~④の順に一組だけ相続人になります。
ちなみに相続人が配偶者のみとか子供のみ親のみの時などは全割合を受け取れることになります。
遺言で法定相続割合とは違う配分を決めることはできる
被相続人がこっそり遺言で「全財産は配偶者に渡す」などと書いてあることがありますが実際にそう書くことは可能です。ただしもしその遺言に不満があればこの場合はまた「遺留分」という法律上の相続人として必ず請求できる権利があります。
※被相続人の兄弟姉妹の相続人にはこの権利はありません。
—
当事務所でも相続や遺産分割協議書についての相談ご依頼を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/