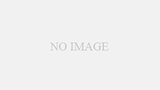こんにちは。先日は令和2年度の行政書士試験が行われましたね。
当方も問題を拝見しましたが難問もあり今回難しい試験だったのだなと思いました。もし、解答速報などで今年度試験の合格は難しいと判断しまた来年受験するおつもりであれば、参考になるか分かりませんが私が行政書士試験で努力したことなどを簡単に記しますのでぜひ一つの情報としてお役立ていただけますと幸いでございます。勉強の合間にでもご覧ください。
独学でも受かるかどうかについて
当方は独学でした。独学でも時間をかければ可能性は十分にある試験だと思っています。
ちなみに、過去に真面目にあまり勉強した方ではなかった方だと思います。
法学初学者、でも受かるかどうか
当方は法学について全くの初学者でした。最初はなかなかなじみのない言葉も多く出てきますが時間をかければ試験合格レベルまで習得させることは可能だと思います。
勉強時間600時間でも受かるものなのか
資格試験の合格までの必要とする標準勉強時間というものがあります。行政書士試験は600時間となっています。600時間で受かる可能性はあります。しかし私は落ちる可能性もあると思っています。すでに合格された方も普通はやはり1,000時間ぐらいかかるという意見が多いように思います。
私が初めて受験したときに、600時間を目安に勉強をし、法律科目はそこそこに理解をできたつもりでいましたが残念ながら落ちてしまいました。2回目の試験で合格しましたがその際は合計1000時間ほどかけていたと思います。でも周りでは500時間ぐらいで受かった方もいるので可能なのだと思います。
私個人としては、もし可能であれば勉強時間はできれば標準時間の倍は勉強するつもりで行っていくのはいかがかと思います。
難しい論点、問題は解けるようにするべきか
難しい問題や出題可能性の低い問題は避けて、やはり基本の問題を解けるようにすべきだと思います。そのためには問題もかなりやりこまないと基本論点が見えてこない気もしますのので過去問はできるだけ解いた方がいいんでしょう。
過去問は何回ぐらい回したかについて
私は過去問についてLECの10年分の過去問を利用しました。他の問題集に比べて分厚いほうだと思いますが、この過去問集を利用ている方が多いのかなと思います。
最終的に私は15周ぐらいしたかもしれません。もちろん苦手な問題についてはさらに多い20週ぐらいしていました。問題自体と論点を覚えるまでかなりやりこみました。
秀才の方はテキストも過去問も1-2回回して合格点を叩き出せるかもしれませんが、私のような凡人はそれ相応の回数はこなした方がいいと思っています。少ない回数でも受かるかもしれませんが、落ちる可能性を下げる為に何回も勉強しました。
テキストについて
どれでもいいと思いますが、今思えば「できるだけ簡単で早く読み終わるもの」にしておけばよかったと思っております。分厚かったり、文字がびっしりと書き込まれているものは大変勉強になりますが、すべて読み終わった時点で1ページ目の内容を忘れている可能性が大だと思います。
なるべく早く読み終えて、問題を解きながらまた見直していくという方が私は有効的だと思いました。そして、またテキストを見直すことは何度見直してもいいので、テキストから調べたりする行為を嫌いになってはいけません。
記述について
試験の記述問題は、運もあると思います。自分が得意な論点ならうれしいですがそうでないとテスト中に青ざめてしまいます。
だから私は、記述の問題集は3冊やりこみました。人によってはそこまで対策はいらないのではないかと思われるかもしれませんが、これは大変勉強になったと思っています。
もちろん問題に対する答えを丸暗記するのでは意味がありませんのでしっかりと把握している条文と問題に対する答えを結び付けられるかがカギになると思います。
問題で実際に聞かれていると、どの条文を結び付ければいいか、など見えていない部分が見えてくることもあると思います。
落ちる可能性を下げる為に勉強しました。
六法は必要か
六法が必要かどうか意見が分かれるところではありますが、私は必要だと思います。テキストに載っている条文で把握だけで事足りそうな気もしますがそれだけだと上記の記述でミスをしてしまいそうな気がしています。
予想模試や会場模試について
どちらにしても必ず一回は受けたほうがいいと思います。でないと時間配分などもまったくイメージできません。
可能であれば、実際に会場に足を運んで行う模試を利用された方がいいと思います。
一般知識対策はした方がいいか
した方がいいと思います。私は一回目の試験で足切りにあってしまったので2回目の試験までに
①新聞をなるべく読むようにした。(時事ネタ対策。試験の年の5月ぐらいまで)
②朝日キーワードを読んで時事ネタに対応できるようにした。
③高校生が使う現代社会の教科書を読んだ
④文章理解対策の問題集をやった
などの対策をしました。そのおかげで14問中12問獲得し貴重な得点源にもなりました。
足切りにあってしまった時は大変ショックでったので、まずはそうならないように対策をされるのをおすすめします。
以上、また思い出したら書き込んでいきたいと思います。
東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/